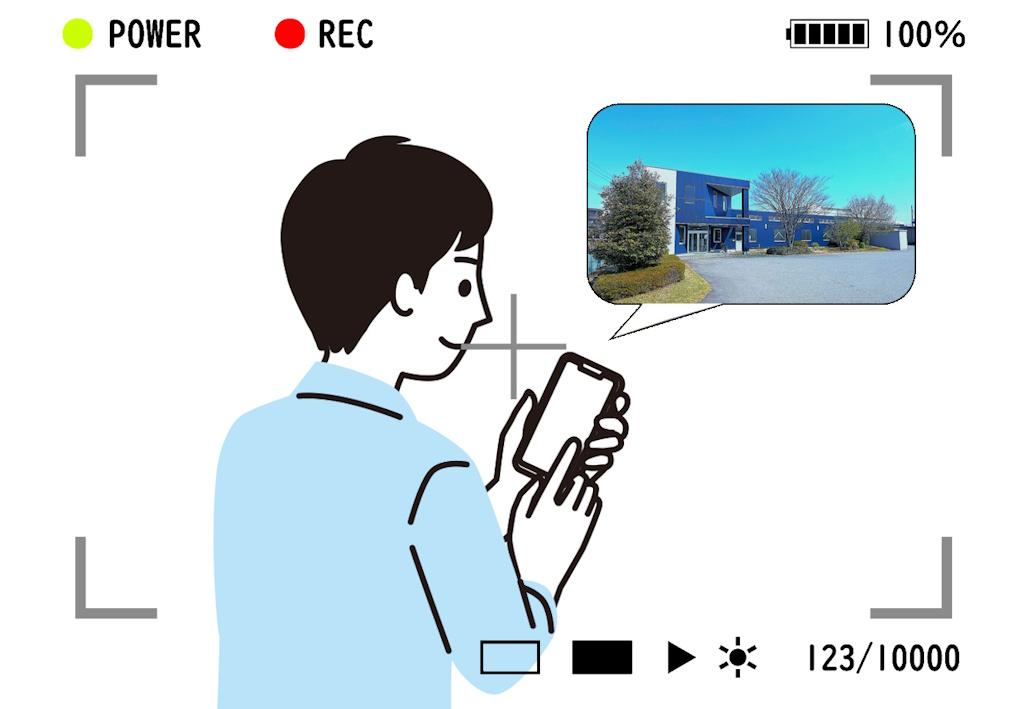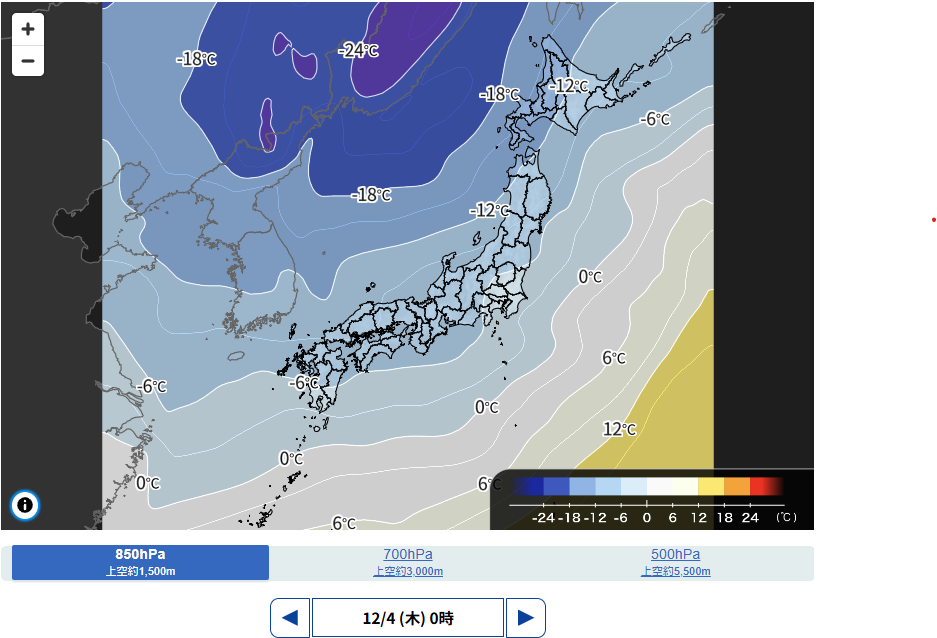回を追うごとに「駄菓子を考える」というところからズレにズレまくっておりますが、少しお許しをいただいて、本日は分別についてでございます。 弊社では社長が社員に毎日駄菓子を配るという妙な慣習がございます。社長曰くコミュニケーション・ツールと申しておりますが、いかがなもんでしょう。 その効果のほどは%$#*=%>¥ さて、その配られる駄菓子は大抵派手なプラの袋に入っているのですが、食べた後は当然ゴミになるわけです。これがまた、量が多い。 製造現場はさておき、事務方の足元にあるゴミ箱にポイポイ捨てられます。 これでは分別もへったくれもありません。 SDG’sとか地球環境を良くしようといくら唱えても足元のゴミ箱からなんとかしなければと。 というわけで、足元のゴミ箱を一斉撤去いたしました。かわりに少し大きめのゴミ箱を事務所の壁際にひとつ置くことにしました。 2段になっていて、プラと燃えるゴミをそれぞれに捨てられるようになっています。 (以前のブログでも他のスタッフが紹介していました) おかげでスッキリしましたが、その後もう一つ問題発生。お菓子の包み紙が、プラごみ入れと燃えるごみ入れの双方に入り混じって捨ててあるではありませんが。 一体どういうことでしょう。 「プラごみはプラごみ入れに入れるのではないか」 「いや、お菓子で汚れているから、汚れているのは燃えるゴミではないか」 「うまい棒とか、さん太郎は中が汚れているけど、中の汚れないお菓子もあるではないか。汚れているのは燃えるゴミでその他はプラごみだろう」 「きちんと分別するのだから、洗ってプラごみに入れるべきだ」 喧々諤々の議論が行われた結果、弊社駄菓子包装ごみ統一ルールが決定いたしました。 小さな個包装プラごみをいちいち洗うのもナンセンス。汚れている汚れていないは確認が難しい。よって、 駄菓子の個包装ごみは燃えるゴミ と、決定いたしました。 しかしながら、私は思うのですよ。 駄菓子の配給を無くせば、問題解決なんですよね。